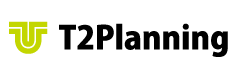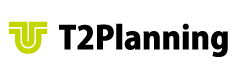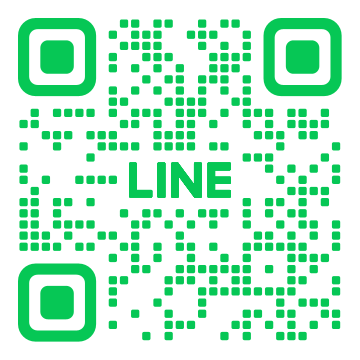外国人の日本での活動範囲
入管法第19条で在留資格で日本に上陸する外国人の活動範囲を定めています。ちなみに入管法の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」と言います。以下入管法と略します。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
まず別表第一を見ないと始まりませんので、ここに記載します。(内容が多いので折りたたんでいます。)
入管法 別表第一
就労系在留資格
上記別表第一の「一・ニ・五」の在留資格で入国する外国人は、原則的に表の右欄の活動以外で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受けることが出来ません。つまり表の右側の活動範囲なら仕事が出来るということです。
反対に別表第一の「三・四」は原則的に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が出来ません。
日本で働くことが出来る在留資格は上記別表の色が付いている「一・ニ・五」が該当し、就労系在留資格と呼ばれることがあります。
原則的にと強調したのは、例外があるからです。次の入管法第19条の第2項を見てみましょう。
資格外活動
出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
別表第一の「一・ニ・五」の在留資格では、表の右に指定された活動範囲外の活動で仕事をすることが出来ないことが原則ですが、本来の活動を阻害しない範囲であれば、活動範囲外の仕事をすることが出来ます。これには別途許可が必要になります。
同じく、非就労系の在留資格である、別表第一の「三・四」の在留資格でも許可を得て働くことが出来ます。例えば留学生であっても許可を得て週に28時間以内のアルバイトをすることが出来ます。
このように活動範囲が定められた在留資格の内、就労系と非就労系に分類することが出来、日本に上陸する外国人の活動がどの範囲に該当するのかを判断することが在留資格を得るための重要なポイントとなってきます。