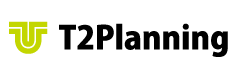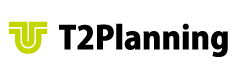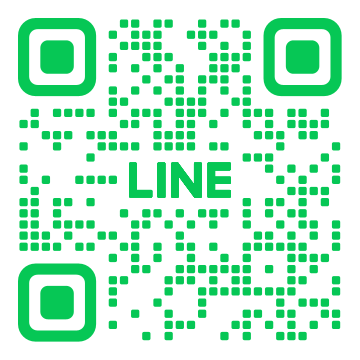特定技能とは
日本国内の人手不足は深刻です。雇用条件の引き上げなど、人材確保の取り組みを行っても人材不足に悩む産業分野において、外国人労働者の受け入れを希望する企業は多くあります。そこで一定の技能を有する外国人を受け入れるために在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が設けられています。
特定技能は入管法別表第一の二に記載されています。
| 特定技能 | 一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
|---|---|
| 二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
このように特定技能とは「特定産業」で「技能を要する」業務に従事する在留資格となっています。
「特定産業」とは人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野とされています。これは1号、2号ともに共通です。しかし、1号で特定産業に指定された産業分野でも2号では指定されていない分野もあります。
特定技能1号
特定技能1号は特定産業分野に関してある程度の知識と経験を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格です。
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとの更新(通算で上限5年まで) |
|---|---|
| 技能水準※1 | 試験等で確認 |
| 日本語能力※2 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 接客を伴うものは日本語能力試験(N3以上) |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない |
| 支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要 |
特定技能1号へのルート
技能実習を経る
技能水準※1と日本語能力※2については、技能実習2号を良好修了した外国人については試験等が免除となります。
技能実習2号を「良好に修了」とは
技能実習2号を「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。
- 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
- 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。
試験に合格する
技能評価試験や日本語能力検定試験を合格することで特定技能1号の在留資格を取ることが出来ます。
日本の日本語教育機関に留学するためにはN5レベルの日本語能力が必要なので、日本語教育機関で学習して試験に合格し卒業後に特定技能1号に在留資格を変更するルートがあります。
外国人本人の能力が特定技能1号の在留資格に必要な要件を持っていることと、受け入れる企業や支援機関の受け入れ態勢も在留資格を許可される要件となるので、提出する書類が多い在留資格であると言えます。
特定技能2号
特定技能2号の対象産業分野は特定技能1号の範囲とほぼ同じですが、必要な知識や技能レベルが格段に上がり、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。受け入れ側企業からすれば即戦力と見みることができます。
特定技能2号では、多くの産業分野で日本語能力についての審査要件を課していません。※3
なぜ日本語能力についての審査要件を課していないのかについて、特定技能2号の在留資格を取得する前提の特定技能2号評価試験は高いレベルの日本語を理解していないと解けませんので、そこで日本語能力を確認できるからだと考えられます。
※3漁業と外食業については日本語能力試験(N3)合格が必要
| 在留期間 | 6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし) |
|---|---|
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 漁業と外食業については日本語能力試験(N3)合格が必要 |
| 家族の帯同 | 配偶者・子は帯同可能 |
| 生活支援の有無 | 支援の必要はない |
特定技能2号の在留資格を持つ外国人は生活支援を受ける必要がなく、まさに手に職を持って日本で生活できる人材となっています。
特定技能の対象となる産業分野
特定技能1号と特定技能2号との関係
特定技能2号は、特定技能1号より深い知識と熟練した技能を持っていることが必要で、上位の在留資格であると言えます。しかし、その知識と経験は、試験によって判定されますので、特定技能1号で経験を積んだからといって特定技能2号へ変更できるような制度はありません。
下の図のように特定技能2号の制度がない産業分野があります。
| 産業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 介護 | 〇 | |
| ビルクリーニング | 〇 | 〇 |
| 工業製品製造業 | 〇 | 〇 |
| 建設 | 〇 | 〇 |
| 造船・船用工業 | 〇 | 〇 |
| 自動車整備 | 〇 | 〇 |
| 航空 | 〇 | 〇 |
| 宿泊 | 〇 | 〇 |
| 自動車運送業 | 〇 | |
| 鉄道 | 〇 | |
| 農業 | 〇 | 〇 |
| 漁業 | 〇 | 〇 |
| 飲食品製造業 | 〇 | 〇 |
| 外食業 | 〇 | 〇 |
| 林業 | 〇 | |
| 木材産業 | 〇 |
令和6年6月の速報値では、特定技能1号で日本に在留する外国人は約25万人となっています。一方特定技能2号で日本に在留する外国人は約150人となっています。
特定技能2号については、まだ人数が少ないですが実務経験が必要であることも関係していると考えられます。特定技能2号評価試験の合格者は増えていますので、今後特定技能2号で在留する外国人は増えてくるでしょう。