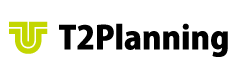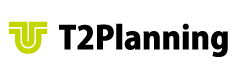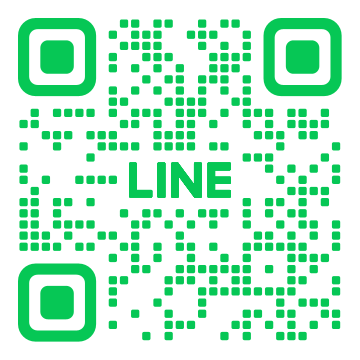会社を設立する際、金銭を出資して株式を取得するのが一般的な方法ですが、中には金銭以外の財産を資本とするなど、特殊な形態での出資や、会社が負担する特定の費用など、設立時の会社の財産内容に大きな影響を与える事項が存在します。これらは会社法上、「変態設立事項」と呼ばれ、厳格な規制の対象となっています。
今回は、この「変態設立事項」について、その具体的な内容と、なぜ厳しく規制されるのか、そしてどのような法的な手続きが必要となるのかを解説します。健全で透明性の高い会社設立のために、ぜひ知っておきましょう。
会社法の規定から学ぶ変態設立事項
変態設立事項とは会社法第28条に規定されている定款への記載事項を指します。変態設立事項は、株式会社を設立する際に通常とは異なる特別な条件を伴う手続きです。この記事では、変態設立事項の概要について解説します。
では条文を見てみましょう。
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一、金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第33条第1項第一号において同じ。)
二、株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三、株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四、株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
会社法第28条では、株式会社を設立する際に、定款に記載または記録しなければその効力を生じないとされる特定の事項を定めています。これらが一般に「変態設立事項」と呼ばれ、主に以下の4つが挙げられます。
- 現物出資
- 金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称、当該財産の内容と価額、そしてその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(種類株式発行会社の場合は、株式の種類および種類ごとの数)を指します。例えば、土地や建物、機械設備、特許権などを現物で出資するケースがこれに該当します。
- 財産引受
- 株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産と、その価額、およびその譲渡人の氏名または名称を指します。会社成立前に特定の財産を会社が買い取ることを約束するような場合です。
- 発起人への特別の利益
- 株式会社の成立によって発起人が受ける報酬その他の特別な利益、およびその発起人の氏名または名称を指します。これは、会社設立の対価として、発起人が不当に高い報酬や利益を受け取ることを防ぐための規定です。
- 設立費用
- 株式会社が負担する設立に関する費用を指します。ただし、定款の認証手数料や、会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定められたものは除かれます。
- 定款に係る印紙税
- 設立時発行株式と引き換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
- 会社法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
- 株式会社の設立の登記の登録免許税
これらの行為は定款への記載がなければ無効になります。(行為が無効になるのであって、定款が無効になるわけではありません。)
なぜ変態設立事項は面倒な手続きが増えるのか。
なぜ「変態」なのか? – 厳格な規制の理由
これらの事項が「変態」と呼ばれるのは、一般的な金銭出資とは異なり、その評価が不明瞭になりやすく、会社の財産が不当に過大評価される(財産が水増しされる)リスクがあるためです。会社の財産が不当に評価されると、将来的に会社が債務を弁済できなくなるなど、株主や債権者を害するおそれがあります。
そのため、会社法はこれらの「変態設立事項」について、会社の財産内容を厳格に審査し、その公正性と透明性を確保するための特別な手続きを要求しています。これは、資本充実の原則を守り、会社を取り巻く利害関係者の保護を図る上で非常に重要です。
会社の設立をする過程で、定款に変態設立事項の記載が必要になると、原則として裁判所への検査役選任の申し立てなどの手続きが増えます。なぜ面倒な手続きが増えるかというと、変態設立事項に挙げられる行為は、発起人間で扱いが不公平になったり、債権者を害する恐れがあるからです。
【図解】現物出資で不正が起きるケース


この例では3人の出資者が1000万円ずつ財産を出資し合って会社を設立しようとしています。
しかし一人が実際には250万円の価値しかない不動産を1000万円の不動産として出資しようとしています。この結果、他の発起人が現金で1000万出資し、1/3の株式を与えられるのに対し、250万の現物出資で1/3の株式を与えられることになってしまします。
また、資本金3000万円となっても実際は2250万円の価値しかないのですから、表示された資本金を信用した債権者を害することになりかねません。
【図解】財産引き受けで不正が起きるケース



財産引き受けとは、会社が成立したあとに行う売買契約です。
この例では3人の出資者が1000万円ずつの財産を出資し合って会社を設立しようとしています。
ひとまず全員現金で3000万円集まり会社が設立されましたが、一人が、会社に250万円の価値しかない不動産を会社に押し付けて、1000万円の現金が流出しています。
これは結果的に、先の例で挙げた現物出資と同じ結果になっています。
財産引き受けの注意点
現物出資をできるのが発起人に限られているのに対し、財産引き受けは発起人以外でも出来る点です。(財産引き受け自体は通常の売買契約ですので、相手方を限定しません。)
会社法第28条1条3号、4号の発起人への報酬や設立費用についても、現金等の財産が流出しますが、報酬や設立費用はコストですので、資本金が減るわけではありません。ですから、実際より過大または不正なコストを計上すれば、会社財産の基礎が揺らぎかねません。
※資本金はその表示どおりの現金や預金が会社に存在しているわけではありませんので注意してください。資本金については以下の記事で触れていますので参照ください。
法的な規制と手続き
「変態設立事項」を設ける場合、以下の法的な規制と手続きが必要となります。
- 定款への記載の絶対的要件
- 「変態設立事項」は、必ず定款に記載または記録しなければ、その事項は効力を生じません。これは、会社の根本規則である定款に明記することで、すべての利害関係者に対しその内容を周知し、透明性を確保するためです。
- 原則:検査役による調査
- 現物出資や財産引受などの変態設立事項は、原則として、裁判所が選任する検査役による調査を受け、その価額が適正であるかどうかの評価・証明を要します。これは、客観的な第三者による厳格なチェックを通じて、財産の水増しを防ぐための重要な手続きです。
- 例外:検査役の調査が不要な場合
- 全てのケースで検査役の調査が必要となるわけではありません。会社法施行規則では、以下のような場合には検査役の調査を要しないと定められています。
- 市場価格のある有価証券の出資: 定款の認証の日における市場価格または公開買付け等の契約価格を超えない範囲の価額であれば、検査役の調査は不要です。
- 特定の設立費用: 前述した定款の印紙税、銀行手数料、検査役の報酬、設立登記の登録免許税など、その性質上評価の必要性が低い費用については、検査役の調査は不要です。
- 弁護士や税理士などの専門家が評価を行った場合など、会社法が定める一定の要件を満たせば、検査役の調査が不要となる場合があります
- 全てのケースで検査役の調査が必要となるわけではありません。会社法施行規則では、以下のような場合には検査役の調査を要しないと定められています。
- 発起人等の責任
- もし出資の履行が仮装された場合、つまり、現物出資の価額が不当に過大に評価されたなど、虚偽の内容に基づいて設立手続きが行われた場合、発起人や設立時取締役はその責任を負うことになります。特に、仮装に関する職務を行った者や、株主総会・取締役会の決議に賛成・提案した取締役などが責任を負うとされています。これは、不正な会社設立を抑制し、関係者の責任を明確にするための規定です。
変態設立事項に関するFAQ
- 現物出資に適用できる資産はどのようなものですか?
-
現物出資に適用できる資産には、不動産、機械設備、特許権などが含まれます。これらの資産は、適正な評価が行われ、その価値が証明される必要があります。
- 変態設立事項を採用するメリットは何ですか?
-
変態設立事項を採用することで、資本金を現金以外の形で調達したり、特定の財産を設立時に取得することができ、設立後の事業運営に有利に働くことがあります。
- 変態設立事項を含む設立手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?
-
現物出資の額にもよりますが、変態設立事項を含む手続きには、評価報告書の作成費用や、専門家の確認費用などが追加で必要となります。
まとめ
株式会社の設立において「変態設立事項」を設けることは、会社の財産内容に大きな影響を与えるため、会社法によって厳格な要件と手続きが課されています。特に、その公正な評価を確保するための「定款への記載義務」や「検査役による調査(またはその免除要件)」、そして「発起人等の責任」は、健全な企業活動の基盤を築く上で不可欠な要素です。
これらのルールを正しく理解し、遵守することで、設立する会社の透明性と公正性が確保され、将来的なトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
変態設立事項を含む会社設立は、通常の設立手続きよりも複雑ですので、適切な準備と手続きを踏むことが大切です。会社設立を検討されている方は、専門家と相談しながら適切な手続きを進めることが重要です。
会社設立や法務でお困りがありましたらご相談ください