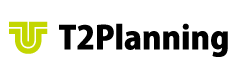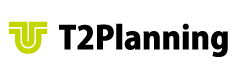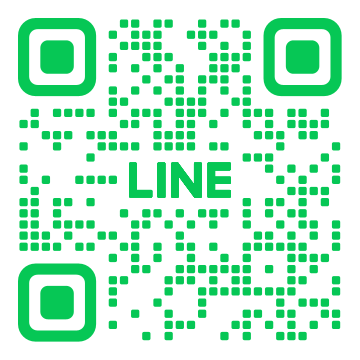自己株式の取得は出資の払い戻しと同様
自己株式の取得は、自社の株主から株を買い取るという行為です。
本来の会社法のルールでは株主は株式を一旦引き受けると、会社の存続中は自分が出資した財産の払い戻しを請求することは出来ませんでした。
しかし、既存の自社株を買い取るということは、株主に対して出資の払い戻しをしていることと同じです。
そこで会社法は、株主間の公平維持や債権者保護の立場から、自己株式の取得には規制を置いています。
株主間の公平
株主間公平の立場から、取引の内容によって決定の仕方が異なります。
債権者保護
自己株式の取得は株主への配当の側面も持ちますので、債権者保護のため分配可能額の範囲で行わなければなりません。
分配可能額を超えて自己株式の取得をした場合には、自己株式の譲渡人である株主、自己株式取得の決定に関わった取締役等に、違法配当と同様の責任が課されます。
ただし、単元未満株式を買い取る場合や組織再編の反対株主への株式買取請求権による買い取りについては規制がないので、分配可能額を超えて行うことが出来ると言えます。
反対株主の株式買取請求権が生じるケースは以下の通りです。
| (1)株式の譲渡制限をする場合(会社法116条1項1号2号) |
| (2)株式に全部取得条項を付す場合(会社法116条1項2号) |
| (3)種類株式の内容として、種類株主総会の決議を要しないと定められた種類株主に損害を及ぼすとき(会社法116条1項3号) |
| (4)株式併合により単元未満を生じる株主(会社法182条の4) |
| (5)会社が事業譲渡を行う場合(469) |
| (6)合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合(785)(797)(806) |
この中で、(1)(2)(3)(4)に当たる株式買取請求権に対しては、次の規定があります。
- 株式会社が第116条第1項又は第182条の4第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法116条1項又は第182条の4第1項の規定による株式買取請求権(上の表の(1)(2)(3)(4))による金銭の支払いが分配可能額を超えた場合は、違法配当と同様の責任が生じます。
第462条と第464条を比較するとわかりますが、業務執行者(取締役等)の責任についてはその責任を規定していますが、株主には会社に対する支払いの責任がありません。