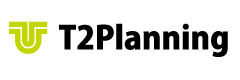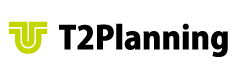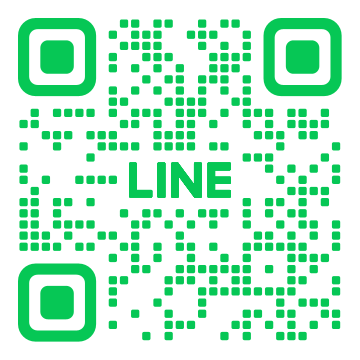本記事では、売買代金が著しく低廉であった第1売買契約が暴利行為として無効とされ、転得者からの明渡請求が棄却された事例を通じて、不動産取引における注意点と法律上の論点を解説します。
東京高裁判決平成30年3月15日の紛争内容
紛争の経緯
東京高裁での平成30年3月15日の判決は、以下のような経緯で争われました。
- 背景と初期の借入れ:
- Y(売主)は70歳の高齢者であり、所有する複数の不動産(自宅、共同住宅、店舗兼共同住宅など)に第一順位の根抵当権を設定してZ農協から約4,880万円を借り入れていました。しかし、返済は滞っていました。
- 平成25年11月、Z農協から「指定期限までに687万円を返済しなければ競売を申し立てる」と通告されたYは、知人から紹介されたA会社の役員Dに相談し、同年12月にAから590万円を借り、延滞分を返済しましたが、指定期限を過ぎていたため、Z農協から残債務約3,000万円の一括返済を求められました。
- 第1売買契約と第2売買契約の締結:
- 平成26年6月9日、YはAに本件各不動産を6,000万円で売却する契約を結びましたが、実際には売買代金の支払いは行われず、Z農協の根抵当権も抹消されないままYからAへ所有権移転登記がなされた。
- 同年7月14日、AはXに対して1億500万円でこれらの不動産を売却しました。Yは第1売買契約後も自宅に居住し続けており、Xも平成26年12月末までのYの居住を容認していました。
- 8月21日に第2売買契約の決済が行われ、Aが受領した代金のうち約3,000万円がYの口座に送金されてZ農協の返済に充てられ、根抵当権が抹消された上で、AからXへの所有権移転登記がなされましたが、それ以外にYへの送金はありませんでした。
- 訴訟の発生:
- 年末になってもYが不動産から退去しなかったため、Xが所有権に基づく建物明渡等を求めて訴訟を提起しました。
各当事者の言い分
- Yの主張:
- 不動産の客観的評価額は少なくとも1億3,100万円であるのに対し、第1売買契約の代金は6,000万円であり、暴利行為として無効である。
- 第1売買契約が無効であるため、転得者Xは不動産の所有権を取得できない。
- Xの主張:
- 第1売買契約は暴利行為に該当しない。
- 仮に無効であったとしても、善意の第三者として権利外観法理(民法94条2項類推)により保護される。
本件の結末
第一審ではXの明渡請求が認められましたが、控訴審である東京高裁判決では以下のように判断され、Xの請求は棄却されました。
第1売買契約の公序良俗違反による無効
控訴審裁判所は以下の事実を考慮し、本件第1売買契約を公序良俗に反する暴利行為として無効としました。
- 不動産の客観的交換価値が1億3,130万円以上であるのに対し、第1売買の代金が6,000万円であり、価格の半分にも満たないこと。
- 第1売買契約によってYが生活の本拠である自宅や収入源であった共同住宅等を完全に失うことになること。
- Yが現実に受け取った現金は皆無であり、代金支払と同視できるのは借入金の返済に充てられた3,580万5,598円に過ぎず、手元に残るものがないこと。
- Yが認知症を発症しており、判断力が低下していたこと。
- D(Aの役員)はYの状況を認識していたこと。
これらの事実を総合的に考慮し、第1売買契約は暴利行為であり、公序良俗に反すると判断しました。
転得者Xに対する対抗問題
裁判所は以下のように判断しました。
- 第1売買契約が無効であるため、Aは不動産の所有権を取得しておらず、したがって転得者Xも所有権を取得できない。
- Xは善意の第三者であるとしても、Yに帰責性が認められないため、権利外観法理による保護は受けられない。
まとめ
暴利行為の要件
暴利行為とは、他人の無思慮窮迫に乗じて不当な利益を得る行為であり、公序良俗に反して無効とされます。本判決では、以下の要件が重視されました。
- 売買代金が客観的価値に比べて著しく低廉であること。
- 売主が窮迫、無経験、認知症等により判断力が低下していたこと。
- 買主がこれらの状況を認識し、不当な利益を得ようとしていたこと。
転得者の立場
第1売買契約が無効とされる場合、転得者も所有権を取得できません。特に短期間での転売がなされる場合、第2売買契約の買主やその仲介業者は、第1売買契約の有効性を慎重に確認することが重要です。
本件は、不動産売買において売買代金が著しく低廉であり、売主の判断力低下を利用した暴利行為が認定された事例です。転得者も保護されないため、不動産取引においては、売買契約の有効性を十分に確認し、慎重に対応する必要があります。
不動産に関するご相談、業務のご依頼のご相談はお問合わせください。