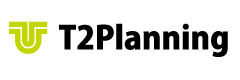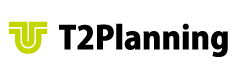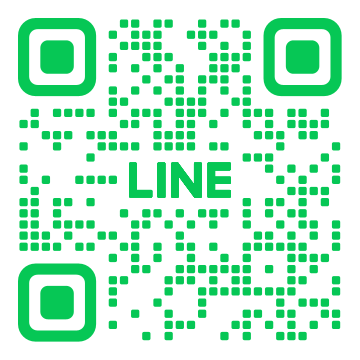賃貸借契約における通常損耗の原状回復義務に関する問題は、入居者と貸主の間でしばしば発生する紛争の一つです。入居者が建物を通常使用した結果生じた損耗について、貸主が入居者にその原状回復費用を負担させることが問題となります。
最判平成17年12月16日
事例の詳細
この事例では、入居者が貸主と賃貸借契約を締結し、3ヵ月分の家賃相当額の敷金を支払いました。契約書には、契約終了時に「修繕費負担区分表」に基づいて入居者が補修費を負担する条項がありましたが、その中に「生活することによる変色・汚損・破損」と明記されており、入居説明会ではこの区分表について具体的な説明はありませんでした。
入居者は約2年半後に退去し、貸主は通常損耗を含めた補修費を敷金から控除して残りを返還しましたが、入居者は敷金全額の返還を請求しました。
当事者の主張
入居者の主張
入居者は、「修繕費負担区分表」に基づく通常損耗の補修費用の負担は、不当な負担を課すものであり、公序良俗に反して無効であると主張しました。
貸主の主張
貸主は、契約自由の原則から、通常損耗の補修費を入居者が負担する特約は有効であり、当事者間でその合意が成立していると主張しました。
判決のポイント
本判決では、通常損耗の補修費用を入居者が負担する特約が成立しているかどうかについて、以下の要件を満たす必要があると判断されました。
- 賃貸借契約書自体に負担する通常損耗の範囲が具体的に明記されていること。
- 貸主が口頭により説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意したこと。
本事例では、契約書や説明会でその内容が明確に説明されていなかったため、特約が成立していないと判断されました。
この判例の重要な点は、賃貸借契約において通常損耗の補修費用を入居者が負担する旨の特約がどのように有効とされるかについて一定の指針を示したことで、貸主と入居者の双方が契約時にどのような合意形成が必要かを理解することが可能となりました。一方で貸主が口頭での十分な説明を怠った場合や、契約書に具体的な記載がない場合には、特約が無効となる可能性が高いことを示しています。
現行法令での原状回復特約について
改正前の民法について従来の通説では、通常損耗の補修費用は賃料に含まれているため、特約がない限り入居者はその費用を負担しないとされていました。改正民法第621条では、通常損耗・経年変化は原状回復義務に含まれないと明文化されました。
入居者は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
これは任意規定であるため、別途特約で通常損耗の補修費用を入居者に負担させる特約を結ぶことは可能です。ただし書面に残せば、特約が有効であるということはなく、前述のように入居者が負担すべき範囲を具体的に明記し、入居者に明確に認識させる必要があります。
消費者契約法との関係
消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています。通常損耗の補修費用を入居者に負担させる特約がこの規定に反するかどうかは、特約の内容が合理的であるかどうかに依存します。
どこまでの特約が有効となるかは判断に迷う部分が残りますが、自然損耗との区別や原状回復費用の負担範囲については、様々な紛争の判例を踏まえて国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠することが望ましいです。あくまでガイドラインなので決まりではありませんが、消費者庁の相談窓口でもこのガイドラインを元に相談を受けている現状がありますので、一般的に共通ルールとして浸透している基準となります。
他の類似判例の紹介と比較
他の類似した判例も参考にすることができます。東京地裁の平成26年5月29日の判決では、賃貸借契約の開始時に貸主が行った補修の内容や、賃料の相場との比較が特約の有効性に影響を与えるとされました。このような判例を通じて、特約の有効性を判断する際の参考になります。
まとめ
この判例は、賃貸借契約における通常損耗の補修費用の負担についての指針を示しています。特約を設ける際には、具体的な明記と入居者への明確な説明が不可欠であり、消費者契約法との整合性も考慮する必要があります。
賃貸不動産の現場は繁忙期に数をこなす営業を取っており、詳細な説明を行うこと難しいでしょうし、入居者が慣れない不動産契約締結の中で内容をどれだけ理解をしなければならないのかという点も問題はあるでしょう。
不動産に関するご相談、業務のご依頼のご相談はお問合わせください。